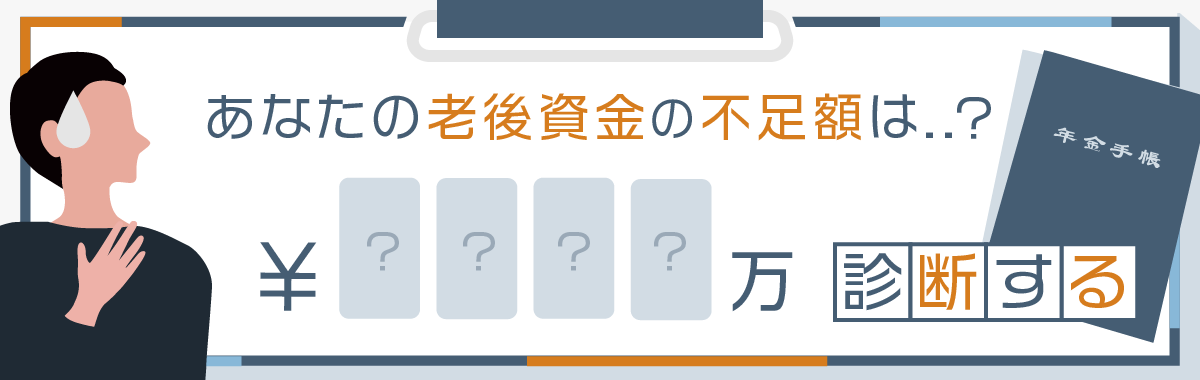老後資金は本当に2,000万も必要?今からどうやって増やせばいい?
取り沙汰されたことで、定年を迎えたあとの老後資金に不安を抱くようになった方は多いのではないでしょうか。不安を抱えながらどう対処すればいいのか、と悩まれている方も少なくないでしょう。老後の資金計画を立てるためには、現役時代のお金の流れから把握することがもっとも大切です。
老後資金のほかにも、人生にはお金がかかる
人生100年と言われていますが、そもそも、人が一生に使うお金は一体いくらくらいなのでしょうか。総務省の家計調査によると、 2023年10〜12月期平均における消費支出(二人以上の世帯) は、1世帯あたり月平均30万6,138円、年間約367万3,656円です。
参照:家計調査報告-2023年(令和5年)12月分、10~12月期平均及び2023年平均-(PDF)|総務省
仮に、20歳から60歳まで40年間同じ金額を支出した場合、単純計算でおよそ1億4,700万円かかることになります。実際の支出は一定ではなく、現役時~定年後にかけて、お金の支出には大きなイベントがいくつかあります。そのときになって慌てないために、ライフイベントごとにかかる費用の目安をチェックしておきましょう。
| 金額 | |
|---|---|
| 結婚費用※1 | 415.7万円 ※新婚旅行含む。全国平均 |
| 出産費用※2 | 約48万円 ※正常分娩のみ/全施設/平均値 |
| 教育資金※3 | 約1,043万円 ※幼稚園~高校公立・大学私立の場合 |
| 住宅購入※4 | 3,719万円(建売住宅) 4,848万円(マンション) |
※1 参照:リクルート ブライダル総研「ゼクシィ 結婚トレンド調査2023」
※2 参照:厚生労働省 保険局保険課「出産費用の見える化等について」
※3 参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
※4 参照:住宅金融支援機構「2022年度 フラット35利用者調査」
イベントによってはまとまったお金が必要になることもあります。急な病気や事故等も起こりえます。そのため、先々を見越して早めに計画の準備をすることが大切です。
いくら貯金をしておけば老後に備えられるのか
日本人の平均寿命から、貯蓄を取り崩す年数を考えよう
厚生労働省(令和4年度)の調べ では、日本人の平均寿命(0歳の平均余命)は男性が81.05年、女性は87.09年となっています。
夫が65歳以上、妻が60歳以上の場合、夫が60歳で定年を迎え65歳で年金の受給を開始したとしても、約20年以上は貯蓄を取り崩す生活が続くことになります。
高齢世帯に必要な生活費の平均
総務省(令和4年)の家計調査によると、65歳以上の単身世帯(無職)の月額消費支出の平均は14万3,139円、65歳以上の夫婦のみの世帯(無職)の場合は 23万6,696円となっています。
参照:統計局ホームページ/家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)
現役時代のように大きな支出のイベントがないとはいえ、定年後の約20年は決して短い期間ではありません。夫婦世帯の月額消費支出から単純計算すると、約5,700万円かかることになります。
特に女性は男性に比べて平均寿命が長いです。所帯で考えるのも大切ですが、個々で計算をしておくことも必要でしょう。
いくらあれば安心? 老後資金の目安を教えます
退職金の計算をしよう
老後の生活費は、公的年金を中心に、不足する分を現役時代に貯めた資金や、退職金を取り崩して賄うのが一般的です。
そのため、退職金もわかる範囲で金額を確認しておきましょう。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者への退職給付額は以下の通りです。
| 大学・大学院卒(管理・事務・技術者) | 1,896万円 |
|---|---|
| 高校卒(管理・事務・技術者) | 1,682万円 |
| 高校卒(現業職) | 1,183万円 |
ただし、これはあくまで目安です。勤めている会社の規模や、勤続年数などによって実際の支給額は大きく異なりますし、退職金のない企業も増えてきています。定年まで勤めた場合の退職金額は勤務先に確認しておくとよいでしょう。
医療が発達し、平均寿命が延びるのは喜ばしいことではありますが、定年退職し、退職金と年金のみで悠々自適に暮らすという勤労者のライフプランが必ずしも成り立たなくなってきています。
求める生活レベルや今の資金状況からあなたの老後に必要な金額を診断します。以下から4問の質問に答えて診断してみましょう!
老後資金を増やすにはどうしたらいいのか
お金には3つの使い道があります。
1つ目は、使う(消費、寄付やお年玉なども)。2つ目は、貯める(預貯金)。3つ目は増やす(資産運用)です。2つ目までは多くの方がおなじみだと思いますが、低金利の金融機関にお金を預けるだけでは、お金を増やすことは難しいでしょう。
超低金利の金融機関にお金を預けるだけでは、物価上昇に追い付かず、実質的に資産価値を目減りさせてしまうことになります。
老後資金についての重要なポイントは、3つ目の“増やす”です。
日常生活での無駄を省いて余った分を貯蓄や資産運用にまわすのではなく、毎月先取りしておくと運用資金を確実に確保することができます。資産運用は余裕資金で行います。そして、それが現役時代から老後までのお金を増やす道になります。
それでは、具体的に公的年金以外で収入を得る方法と、メリットとリスクおよびデメリットについて説明します。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
事業主が決まったルールに基づき、掛金を拠出します(従業員が上乗せ拠出できる会社もある)。従業員自身が運用商品を選んで、その運用結果によって将来受け取る年金額が変わる制度です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
企業型確定拠出年金と仕組みは同じです。毎月の掛金の金額は自分で決め、自分で運用します。
月々5,000円と少額から積立可能ですが、運用次第では元本割れするリスクのある商品もあります。掛金は、全額所得控除されるため課税はされません。2017年以降は公務員や専業主婦も加入できるようになりました。
原則として、60歳までは資金を引き出すことはできません。継続して掛金を拠出することが難しくなった場合には、それまでの積立金の運用を続ける必要があります。
NISA
株式や投資信託など金融商品への投資で得た利益や配当に対して、本来かかる約20%の税金がかからなくなる制度です。2024年から制度が新しくなり、無期限で生涯1,800万円までの投資ができるようになりました。
個人年金保険
保険は、将来起こるかもしれない事柄に対し、加入者が保険金を出し合い、万一に対して備える制度です。公営保険と民営保険があります。
個人年金保険は、個人が公的年金で不足する部分を補うために、民間の保険会社などが用意している保険商品です。
契約時に、年金の受け取り時期に受け取る金額があらかじめ決まっている定額年金や、将来の運用成績によって受取額が変わる変動年金、また年金の受け取り期間が5年、10年、20年などと固定されている確定年金か、生きている間ずっと受け取れる終身年金などがあります。
メリット
- 満額や一時金:予定していたときにまとまったお金が確保できます
リスク・デメリット
- 定額の支払い:契約直後から定額での支払いが発生するため、ライフスタイルが変わった時に生活費を圧迫する可能性があります
- 中途解約による解約手数料:契約期間中に解約した場合、解約手数料が発生する商品があります
- 貯蓄型商品の手数料:ほかの外貨建て金融商品に比べると割高な商品があります
株式投資
企業が発行する株を売買し、利益を得ようとすることです。
メリット
- 値上がり益:購入時より株価が上がったときに売れば、購入価格と売却価格の差分が利益になります(キャピタルゲイン)。元本が大きく増える可能性があります
- 配当金:株の保有中は、企業の利益の一部を配当金(インカムゲイン)として受け取れます
- 株主優待:株の保有中は、配当金や株主優待品(自社製品やQUOカードなどが多い)が受け取れます。株主優待制度のない企業もあります
リスク・デメリット
- 価格変動リスク:購入時より株価が下がったときに売ると、損失が発生します
- 為替変動リスク:外国株式等に投資した場合、売る時の為替相場によっては価値が目減りします
- 信用リスク:投資した企業が破綻する可能性があります
- カントリーリスク:投資対象国の政治、経済情勢の不安定化などのに影響を受け、投資元本の回収不能、または、投資した金融商品などの価格変動によって損失を被る可能性があります
投資信託
人々から小口のお金を集めて大きな資金とし、それを運用の専門家が投資・運用し、投資額に応じた分配金が得られる商品のことです。
メリット
- 1万円からなど、少ない金額から始められます
- 株式や債券など、個人では投資が難しい対象にも、複数の資産に対して分散投資ができます
- 運用の専門家に任せられます
リスク・デメリット
- (株式投資と同様に)価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、金利変動リスク、カントリーリスクがあります
- 国内外の株式、債券、不動産など投資対象がたくさんあることはメリットにもなりますが、ファンドの数が多すぎて、経験が浅いと何を基準に選んだらよいか迷います
- 運用をプロに任せるので、自分の意思は運用成績には反映されません
FX
Foreign Exchange(外国為替証拠金取引)の略で、ほかの国の通貨を売買して利益を出す仕組みです。
メリット
- 証拠金を担保に、少ない資金で最大25倍(個人の場合)までの外国為替の取引をすることが可能です(レバレッジ効果)
- 外貨預金と比べて、為替手数料(スプレッド)が安いです
- スワップ金利における利息を受け取れる可能性があります
リスク・デメリット
- FXの特徴であるレバレッジ効果により、逆に不利な方向に相場が変動すると、大きな損失を出す場合があります。預け入れた証拠金の額を損失が上回ることがあります
- ロスカットリスク:証拠金が50%、80%、100%など、各社の基準に到達すると、意図せず強制的に決済されます
- 金利差における損失を被る可能性があります
不動産投資
現物の不動産を購入し、入居者を募集し家賃収入(インカムゲイン)を得ることです。
メリット
- 毎月、安定した家賃収入:入居者が決まれば毎月安定した入金があります
- 不動産売買の時に生じる利益:購入時より土地建物が高く売れた場合に利益が生じます(キャピタルゲイン)
リスク・デメリット
- 空室リスク:想定していた家賃が入らないことがあります
- 災害リスク:災害によって土地建物が被災することがあります
- 流動性リスク:不動産の売買は数か月以上かかるため、急な換金が難しいです
「増やすアクション」を始めてみることが大切
いくつかの投資方法をみてきましたが、共通して言えることは、投資を始めなければリターンもない、ということです。
時間とお金に余裕ができる定年後に、いざ老後資金の運用を始めようと思っても、いきなり上手にはできませんし、増やす時間も限られてしまいます。
また投資のリスクとリターンは、大きなリスク=大きなリターン(安全性が低い)、小さいリスク=小さなリターン(安全性が高い)とトレードオフの関係になります。
投資とは何? 種類から初心者向けおすすめ方法まで解説
リスク回避をするためには、知識を得ることが大切です。投資方法や投資先を絞りすぎず、資産をさまざまな種類の投資に分散すること、さらに、時期を分散することが大事です。
資金を一度に投入してしまうのではなく、何度かに分けて投資をすることで買値を平準化できるため、高値で買ってしまうようなリスクを抑えることができます。このような形をとりながら、中長期的な投資を行うことが、リスクコントロールにつながります。
まとめ
公的な調査結果も参考にしながら、ご自身の現在の年齢に合わせてシュミレーションを設定し、老後の資金を増やす方法を考えましょう。
現在の自分のライフスタイルに合った投資方法を選びましょう。資産運用のセミナーや、マネーセミナーなどでプロに無料の相談をしてみるのもおすすめです。RENOSYに資料請求していただくと、今さら聞けないお金の基本的な知識を「図解でわかる!老後のためのあんしん投資」でもわかりやすく解説しています。
【ウェブ資料を見る】 図解でわかる! 老後のためのあんしん投資
その他、公的年金以外にも収入を得る方法として、老後も仕事を続けるという選択肢もあるでしょう。なかなか将来の自分がどのような仕事についているかなどと想像するのは難しいです。そこで、今現在、60歳以上で活躍されている方を男女問わず探してみてください。
もちろん、将来は状況も変わりますので、その方たちの仕事がその時に存在しているかはわかりません。しかし、その先輩の生い立ちなどから、何歳でどうアクションを起こしていたかなど、参考にできる部分はあるのではないでしょうか。
そしてお金を「増やす」投資について知り、自分自身の資産計画を練ることによって、お金について自分自身で判断できる姿勢が身につきます。
正しいお金の教養を身につけることによって、老後の生活への不安を減少させ、自分らしい豊かな生活を送りましょう。
※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
関連キーワード