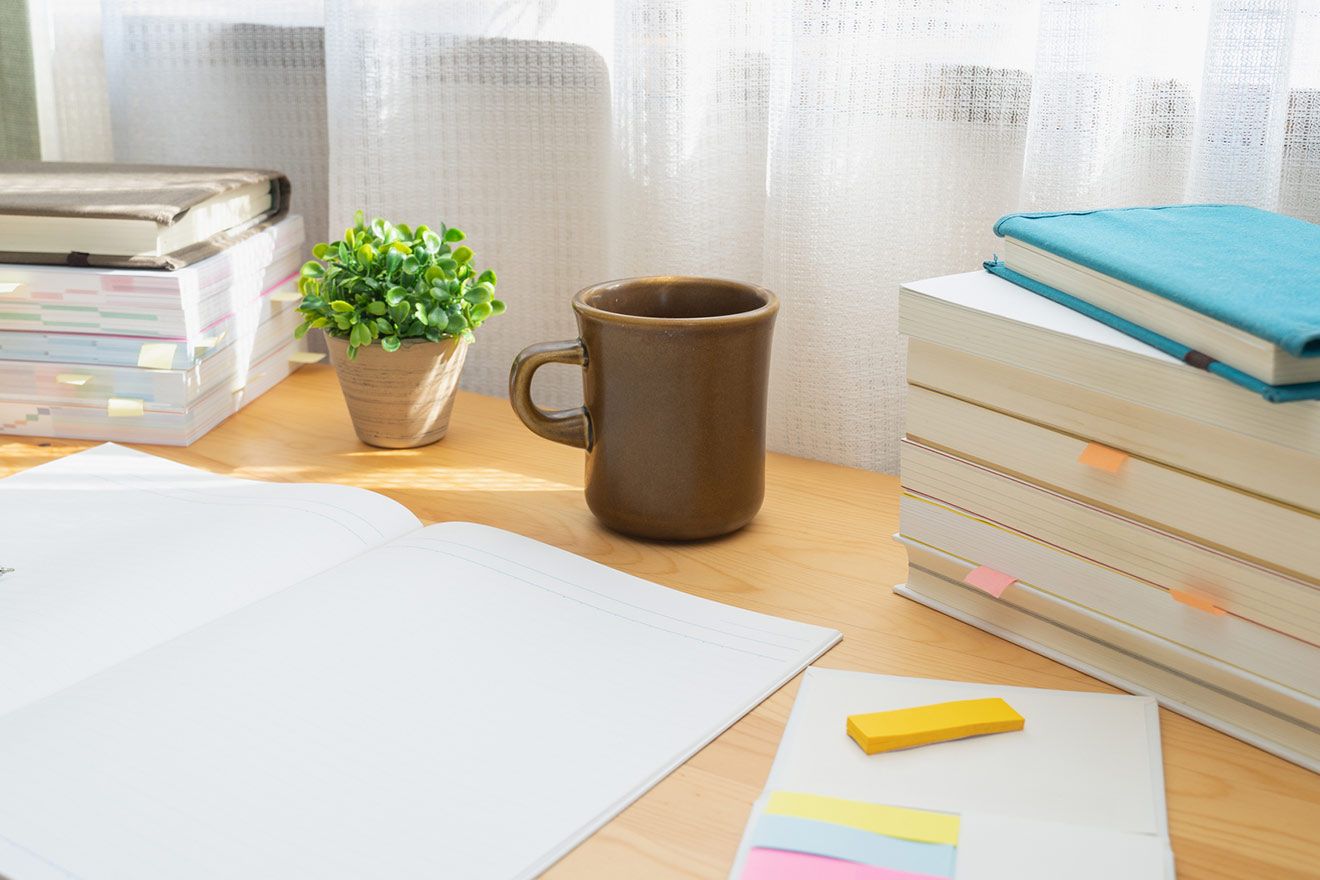不動産投資に宅建はいらない? 取得するメリット・デメリットを解説
不動産投資を始める際、知識を身につける一つの手段として「宅地建物取引士(以下、宅建士)」の取得を考える方もいるでしょう。
宅建の取得は、不動産投資に必須なわけではありません。宅建資格を必要とする業務は、不動産会社に委託するものが多いためです。
ただ、宅建を通して得られる知識が、役立つ場面はあります。
本記事では、不動産投資における宅建の必要性や、取得するメリット・デメリット、資格の取得以外で不動産投資を成功させるポイントを解説します。
宅建(宅地建物取引士)とは?
宅建とは「宅地建物取引士(宅建士)」の略で、不動産取引に関する専門知識を証明する国家資格です。資格を持つ宅建士は、不動産の売買や賃貸契約において以下3つの法律で定められた独占業務を行えます。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書(35条書面)への記名
- 37条書面への記名
不動産会社では一定数の宅建士の配置が義務づけられている資格です。また、不動産投資を行う個人にとっても、民法や宅地建物取引業法(以下、宅建業法)どを理解できるようになるため、契約内容への理解も深まることが見込まれます。
宅建の資格取得方法
宅建士の試験は年に一度、例年10月第3日曜日に実施されます。受験資格は定められておらず、学生や主婦、サラリーマンなど誰でも受験可能です。試験はマークシート形式の学科試験のみで、合格率の目安は16%前後です。
宅建士として独占業務を行うためには、試験に合格するだけでは不十分です。2年以上の実務経験、もしくは登録実務講習を修了する必要があります。最後に宅建士証の交付を申請し、受け取ることで、宅建士として活動を始められます。
不動産投資に宅建はいらない?
不動産投資を始めるにあたって宅建士の資格は法律上必要ありません。不動産投資は物件を購入・運用して収益を得る行為であり、契約書への記名や重要事項説明などの宅建士の独占業務とは無関係であるためです。実際、多くの投資家は資格を持たずに運用を行っています。
ただし、宅建の勉強を通じて得られる知識は契約内容の理解やトラブル回避に役立ち、交渉時にも有利になる場面があるかもしれません。一方で、資格取得には多くの時間と労力、また費用もかかるため、目的と投資スタイルに応じて判断することが重要です。
不動産投資で役に立つ? 宅建を取得するメリット
不動産投資において宅建士の取得は必須ではありませんが、メリットも存在します。
- 法律への知識を深められる
- 重要事項説明書の内容を深く理解できる
- 非宅建業者からの不正な行為を見極められる
- 取引先との交渉を有利に進められる
- 信頼できる不動産会社を見極められる
順番に解説します。
1. 法律への知識を深められる
宅建の資格試験の学習により、民法や宅建業法、建築基準法など法律への理解を深め、結果として物事をより多角的に捉えることができるようになります。
物件の価値は、駅からの距離や築年数だけで決まるわけではありません。その土地がどのような使われ方を想定した土地なのか、「どのような建物を」「どれくらいの規模で」建てられるかといったことも理解できるようになります。
「建ぺい率」や「容積率」の知識があれば、購入を検討している中古物件が、現在の法律の基準を超えて建てられている「既存不適格建築物」である可能性にも気づけるでしょう。不動産を評価する力を養えるといえます。
2. 重要事項説明書の内容を深く理解できる
不動産取引においては、契約前に宅建士から受ける重要事項説明というものがあります。重要事項説明では、不動産に関する重要な説明(売買の対象となる物件や取引にかかわる内容などの説明)が行われます。宅建資格を取得することで、専門用語で埋め尽くされた書類を自らの力で深く理解し、物件に潜むリスクを正確に評価できるようになります。
知識がなければ、ただ説明を聞くだけになりがちです。しかし、不動産の知識があれば能動的にリスクを洗い出す機会に変えられます。高額な投資の失敗を防ぐための、価値あるスキルとなる可能性が高まるでしょう。
3. 非宅建業者からの不正な行為を見極められる
宅建業法は、知識の少ない消費者を保護するため、不動産会社の業務や勧誘方法に厳しい規制を設けています。このルールを知っていることで、相手の言動が法的に許される範囲を超えているかを自身で判断し、不当な要求を拒否する根拠を持つことが可能です。
たとえば、営業担当者から執拗に契約を迫られたとしても、宅建業法で禁止されている「契約を強要する行為」にあたる可能性を疑い、冷静に対処できます。
不動産投資の世界には、知識の乏しい投資家を狙った悪質なグループが存在するのも事実です。宅建士の知識は、そうした悪意のあるグループの甘い言葉や強引な手口の裏に隠されたリスクや違法性を見破る役割を果たし、トラブルを未然に防ぐスキルとなります。
4. 取引先との交渉を有利に進められる可能性も
専門知識は、交渉を有利に進めるための武器になり得ます。不動産取引の交渉は情報戦であり、専門知識の差がそのまま交渉力の差になることもあります。
法律や業界の慣行を理解していることで、相手のペースに飲まれることなく、自身の要求を論理的に伝えられます。
交渉において重要なのは、感情論や漠然とした希望ではなく、客観的な根拠です。不動産の専門知識により根拠を導き出せれば、自信を持って交渉の場にのぞめます。
5. 信頼できる不動産会社を見極められる
不動産投資の成功は、よいパートナー選びにかかっていると言っても過言ではありません。宅建業法に関する知識は、数多く存在する不動産会社の中から、法律を守り、顧客のために誠実な業務を行う信頼できるパートナーを見極めるための客観的な判断基準となります。
たとえば、重要事項説明の場面で、宅建士が質問をはぐらかしたり、説明を急いだりするようなら、その会社は信頼に値しないと判断できるでしょう。
信頼できるパートナーを選ぶためにも、物件の紹介内容だけでなく、その会社の業務プロセスが法律に則って誠実に行われているかを観察することも大切です。
不動産投資のために宅建を取得するデメリット
不動産投資のために宅建士を取得する際にはデメリットも存在します。
- 勉強時間を確保する必要がある
- コストがかかる
- 合格率が低く、狭き門である
順番に解説します。
1. 勉強時間を確保する必要がある
宅建資格の取得を目指すうえで、多くの方が最初に直面するのが勉強時間の確保です。個人差はありますが、宅建試験の合格には少なくとも300時間程度の学習が必要とされています。
300時間の学習を試験までの6カ月間(約180日)で達成する場合、1日あたり約1.7時間の勉強が求められます。本業で働きながら、あるいは家庭と両立しながら、この学習時間を継続するのは簡単ではありません。
資格取得を検討する際は、まずご自身の生活スタイルの中で、この学習時間を現実的に確保できるかを冷静に考えてみることが重要です。
2. コストがかかる
時間だけでなく、金銭的なコストもかかります。資格取得には、学習教材の費用だけでなく、受験料や合格後の登録料など、さまざまな場面で費用が発生するためです。
宅建士の取得にあたってかかる費用の目安は以下のとおりです。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 学習費用 |
|
| 手数料(令和6年時点) |
|
| 資格維持費用 | 宅建士証は5年ごとに更新が必要で、その都度、法定講習の受講などで1万6,500円程度の費用が発生。 |
必要な費用を事前に把握し、自身の予算計画に組み込むことが不可欠です。
3. 合格率が低い
多くの時間と費用を投資しても、必ず合格できるとは限らないのが、宅建試験です。直近12年の合格率平均は16%前後で、宅建試験が狭き門であることを客観的に示しています。
受験資格に制限がないため、準備不足の受験者も多く含まれることを考慮しても、試験自体の難易度が高いことがうかがえます。
また、合格基準点は毎年変動するため、「何点取れば確実に合格」とはいえない不確実性も、受験者にとっては大きなプレッシャーとなるでしょう。宅建取得に挑戦するのであれば、不合格になる可能性も覚悟のうえで、腰を据えて取り組む必要があります。
不動産投資で宅建業法違反になるケースはあるの?
不動産投資は宅建士を取得していなくても個人で行える行為です。ただ、取引の内容や頻度によっては宅建業法に該当し、宅建業法違反となる可能性もあり得ます。特に注意すべきなのが以下の2点です。
- 反復継続性
- 利益目的(事業性の高さ)
不動産投資で売買を繰り返すと「事業性が高い」とみなされ、宅建業の免許がないまま取引を続けると、違法と判断される可能性があります。
国土交通省も「反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い」と明記しています。
ただし、取引回数や金額などの明確な基準はありません。過去の実績や将来的な計画も含めて、総合的に判断されます。複数回にわたる売買を予定している方は、宅建の資格を取得しておくと安心です。
宅建の取得以外に不動産投資を成功させるポイント
宅建の取得以外に不動産投資を成功させるポイントは、主に以下の5つです。
- 目的を明確化する
- 不動産投資のリスクを把握する
- 綿密なシミュレーションを行う
- 分散投資をする
- 信頼できる不動産会社を選ぶ
順番に詳しく解説します。
1. 目的を明確化する
不動産投資を始めるとき、魅力的な物件情報ばかりに目が行きがちですが、目的を具体的に設定することが大切です。目的が曖昧なままでは、不動産会社の営業トークや、目先の利回りの高さに振り回され、最適ではない物件を選んでしまうかもしれません。
たとえば、毎月の安定した家賃収入を得たいのか、将来の値上がりによる売却益を狙いたいのかによって、選ぶべき物件は大きく異なります。まずは、「いつまでに」「どのような資産を」「いくらくらい」築きたいのか、投資のゴールを具体的に書き出してみましょう。
2. 不動産投資のリスクを把握する
投資の世界では、リターンとリスクは常に表裏一体です。不動産投資の成功は、大きな利益を期待するだけでなく、それに伴うさまざまなリスクを正しく理解し、事前に対策を講じられるかにかかっています。
不動産投資の主なリスクと対策は以下のとおりです。
| 空室リスク | 物件購入の段階で、長期的に需要が見込まれそうな立地の物件を選ぶ |
|---|---|
| 修繕リスク | あらかじめ修繕費用を収支計画に盛り込む |
| 金利上昇リスク | 投資初期に頭金を入れるか、繰上返済を検討する |
不動産会社からメリットばかりを強調されたとしても、必ず自身でデメリットやリスクを考え、一つひとつ解消していく姿勢を持つことが大切です。
3. 綿密なシミュレーションを行う
物件の購入を決断する前には、不動産会社が提示する表面利回りを鵜呑みにせず、綿密な収支シミュレーションを行うことが重要です。投資で本当に大切なのは、売上ではなく手元に残る利益です。
シミュレーションでは、満室時の家賃だけでなく、周辺の空室率を考慮した現実的な収入を見積もります。支出面では、管理委託料や固定資産税、修繕費といった運営経費に加え、ローン返済額も全て計算に含めるとより詳細な計画を立てられます。
4. 分散投資をする
不動産投資で一つの物件に集中しすぎると、空室リスクや価格変動の影響を大きく受ける可能性があります。そこで有効なのが、資産を複数の投資先に分ける「分散投資」です。
エリアや物件タイプ、築年数などの異なる複数の不動産を保有することで、不動産投資におけるリスクを軽減できます。また、経済状況や需要の変化にも柔軟に対応でき、収益の安定化が期待できるでしょう。
資産全体のバランスを考えながら、戦略的に物件を増やしていくことが、不動産投資成功の鍵となります。
5. 信頼できる不動産会社を選ぶ
不動産投資を成功させるには、どの会社と組むかにかかっています。不動産会社の信頼性は、担当者の説明の質や提案内容、契約プロセスの透明性といった業務の随所に現れます。宅建の勉強を通じて得た知識は、その良し悪しを判断する確かな「物差し」となるわけです。
信頼できる不動産会社を選ぶことは、成功への最短ルートです。会社の規模や知名度だけでなく、担当者個人の知識や誠実さを含め、複数の会社を比較検討しましょう。
不動産投資の目的に合わせて宅建の取得を検討しよう
不動産投資を成功させるために、宅建士の資格は法的に必須ではありません。しかし、取得することでリスクの高い物件や不利な契約条件を、業者任せにせず自らの力で見抜く判断力を養うことが可能になります。不動産会社と対等な立場での交渉ができれば、より確実な資産形成へと近づくことになります。
一方、資格取得には相応の時間と費用がかかります。積極的に不動産売買に関わっていくのか、ご自身の投資スタイルによって資格の重要度は変わってきます。
メリット・デメリットを踏まえたうえで、自信で宅建の必要性を判断できれば、不動産投資の成功に一歩近づけるでしょう。
※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
関連キーワード