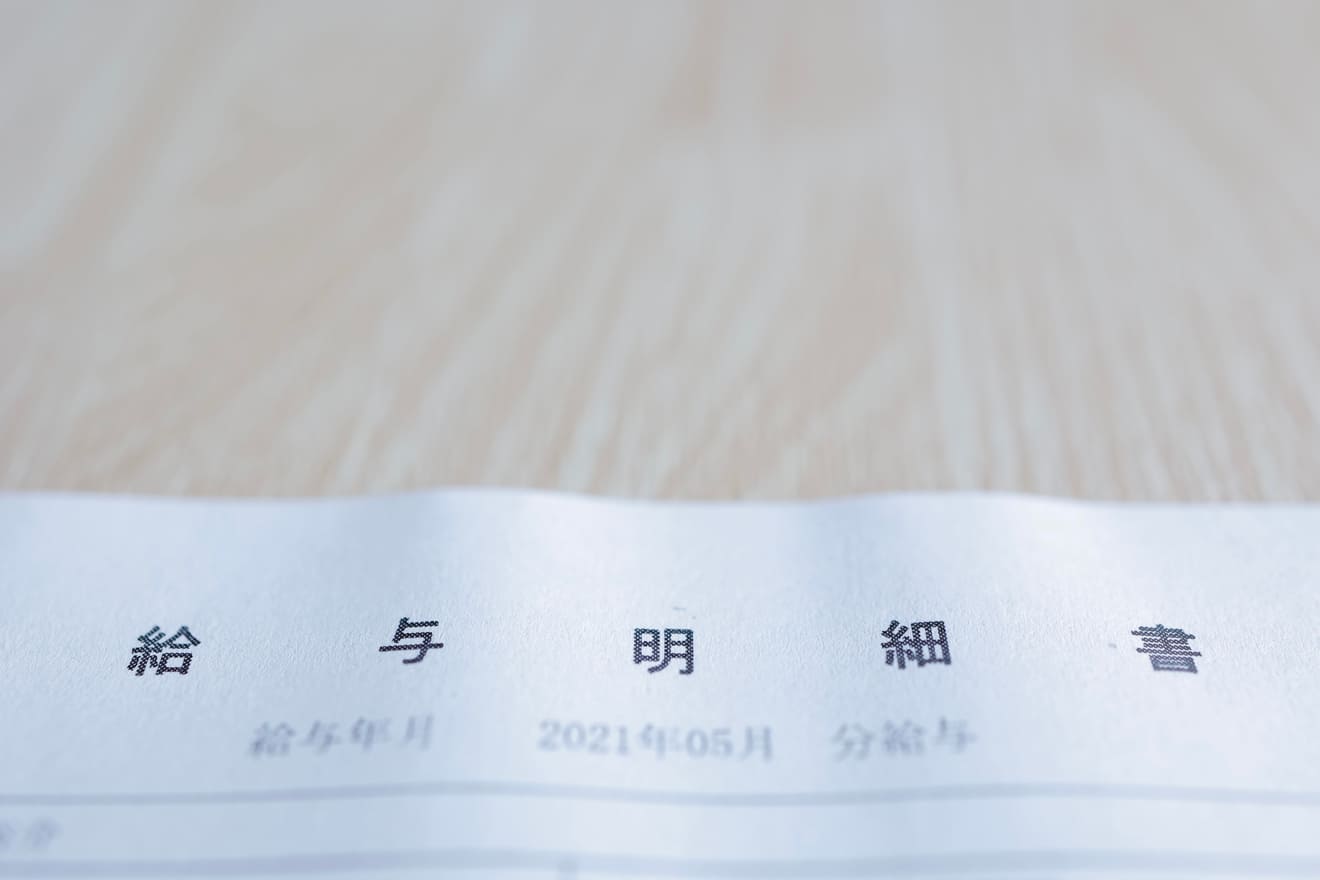住民税の支払い方がわからない! 住民税の支払い方法や時期などを解説
サラリーマンの場合は通常、住民税は会社の給与から天引きされますが、なかには自分で納めなくてはならない人もいます。住民税の支払い方がわからないという人に向け、住民税の支払い方法や時期などを解説します。
CONTENTS目次
住民税とは
会社員の場合、所得税や住民税は会社が支払う給与から天引き(源泉徴収)されるため、住民税についてあまり詳しく知らないという人も多いと思います。住民税とは何か、また目的や種類などを解説します。
住民税の目的
住民税とは、1月1日時点の住所地の自治体に納める税金です。1月1日時点の住所地なので、例えば3月に引っ越した場合、翌年の1月1日を迎えるまでは納税先が以前の住所地となるので注意しましょう。
会社員の場合は源泉徴収なのであまり気にかけていない方も多いかもしれませんが、所得税は国税、住民税は地方税という点で異なります。
国税は国の行政サービスを、地方税は自治体の行政サービスを運用する目的で徴収されます。
住民税の種類
住民税は均等割と所得割の大きく2種類に分かれ、合算して納税します。
均等割とは、所得に関係なく納税義務者が均等に負担する住民税で、道府県民税1,000円と市町村民税3,000円に森林環境税1,000円を合算した5,000円が標準税率です。
所得割とは、前年の所得に応じて納税者の負担額が変化する住民税のこと。所得割の標準税率は道府県民税4%と市区村民税6%(政令指定都市は道府県民税2%、市民税8%)を合算した10%です。
自治体によっては条例を定めて独自の税率を設定しているところもあるため、税率を詳しく知りたい場合は住所地の自治体に確認しましょう。
住民税の徴収方法
住民税の徴収方法は普通徴収と特別徴収の2つです。それぞれの徴収方法について説明します。
普通徴収
普通徴収は、個人事業主やフリーランスなどが対象です。5月~6月に自宅に届いた「住民税決定通知書兼納付書」で、自ら住民税を一括または4期に分けて納付します。
普通徴収の場合には、自ら住民税を納付しなくてはならないため、納付忘れに注意しましょう。
特別徴収
特別徴収は、会社勤めのサラリーマンが対象です。会社が毎月従業員の給与から住民税を天引きして納付します。
個人事業主やフリーランスが対象の普通徴収とは異なり、原則として自分で住民税を納める必要はありません。そのため、普通徴収のように納付を忘れるという心配はないでしょう。
不動産投資による所得と住民税の関係。計算の仕組みと納税のポイント
住民税の支払い方法
住民税の支払い方法は、どのような住民税の徴収方法が適用されるかによって異なります。続いて住民税の支払い方法について解説します。
特別徴収は源泉徴収
特別徴収は、会社が従業員に代わって給与から住民税を天引きし、翌月10日までに納付します。
会社勤めの場合は、原則として特別徴収が適用されるので、ほかの納付方法は選択できません。
普通徴収は納付方法を選択可能
普通徴収は自分で住民税を納めます。そのため、複数の選択肢から住民税を納める方法を選ぶことが可能です。
自治体によって選択できる納付方法は異なりますが、現金納付、Pay-easy(ペイジー)、クレジットカード払いなどが挙げられます。
どのような納付方法が選べるのかについては、自分が住む自治体に確認しましょう。
現金納付
普通徴収の場合、5月~6月にかけて「住民税決定通知書兼納付書」が届きます。現金納付の場合、届いた納付書をコンビニや金融機関などの窓口に持参し、住民税を納付します。
現金納付の場合には、コンビニや金融機関の窓口に行かなくてはならないため、時間と手間がかかる点がデメリットです。近くにコンビニや金融機関がない場合は、ほかの方法を選択することをおすすめします。
Pay-easy(ペイジー)
住民税の納付がペイジーに対応している自治体の場合は、インターネットバンキングやモバイルバンキングなどからの納付が可能です。インターネットバンキングやモバイルバンキングの場合、自宅にいながら納付できるので時間と手間を省けるでしょう。
クレジットカード払い
クレジットカード払いに対応している自治体の場合は、カード払いを選択すれば、納税額に応じてカードのポイントが貯まります。
現金納付やペイジー払いを選択した場合は、単に支出が生じるだけでカード払いのような還元はありません。
お得な住民税の納付方法ですが、すべての自治体が対応しているわけではないので注意が必要です。
納付が遅れた場合のペナルティー
特別徴収の場合は、給与からの天引き(源泉徴収)なので納付が遅れる心配はありません。しかし普通徴収の場合は、自ら納付するので納付が遅れる可能性があります。もし納付が遅れた場合にはどんなペナルティーが適用されるのか見ていきましょう。
延滞税が課される
延滞税とは、税金を納めなくてはならないにもかかわらず納めなかった場合に、納付が完了するまで上乗せされる税金で、住民税も対象です。延滞税が課される主なケースとして、以下の3つが挙げられます。
- 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納していない
- 期限後申告や修正申告をした場合で、納付しなければならない税額がある
- 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額がある
延滞税の税率は、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは原則年7.3%か延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い税率、2カ月を経過した日以降は年14.6%か延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い税率です。
延滞税は仕組みが複雑なので、詳細を知りたいという場合は国税庁のサイトを確認しましょう。
住民税の納付忘れに注意しよう
特別徴収の場合は給与からの源泉徴収なので、住民税を納付し忘れる事態が起きることは基本的にありません。
しかし普通徴収の場合には、自分で住民税を納めなくてはならないため、納付忘れが起きる可能性が高いでしょう。
納付忘れが起きた場合には、延滞税などのペナルティーが発生するので、住民税の納付を忘れないよう注意が必要です。
・住民税決定通知書とは? いつ発行されるか再発行できるのかなどを解説
・住民税が高いのはなぜ? 住民税の仕組みと高くなった理由について解説
・住民税はいつからいつまでが対象? 負担額が変わる要因も紹介
※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
関連キーワード