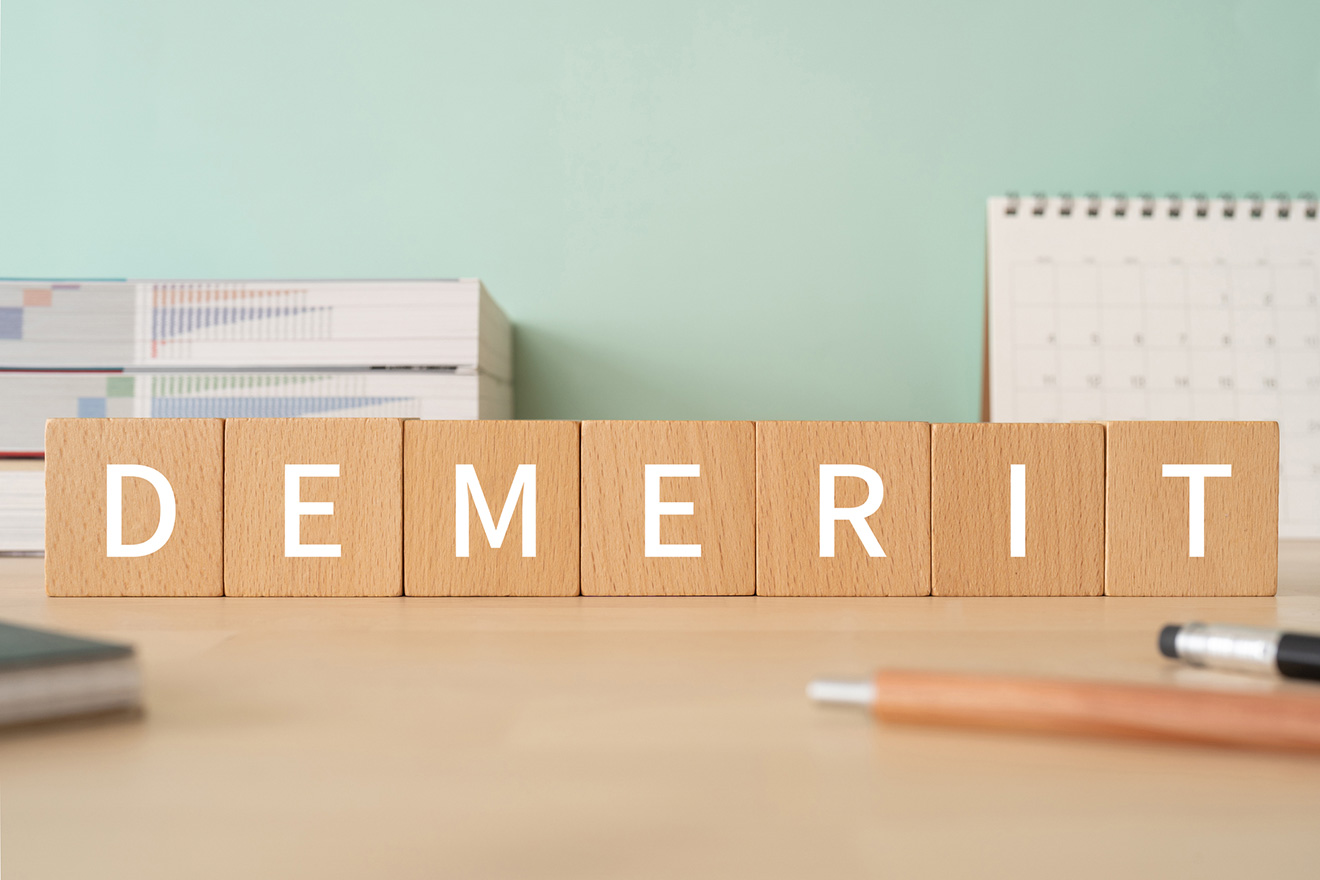不動産投資は個人事業主として行うのがいいのか? メリットや法人化のタイミングも紹介
不動産投資を検討している方のなかには、不動産賃貸業を法人化し、個人事業主として活動している方がいます。個人事業主として不動産投資を行うことで、青色申告特別控除を受けられたり、3年以内の赤字を繰り越せたりと、いくつかのメリットがあります。
また所得額によっては、法人化により大きなメリットを得られるかもしれません。本記事では、個人事業主で不動産投資をするメリットや注意点、法人化するタイミングなどを詳しく解説します。
サラリーマンの不動産投資は個人事業主が有利なのか?
不動産投資を行うサラリーマンが節税メリットを最大化したい場合、開業届を提出して個人事業主となり、青色申告を選択することが有効です。開業届を提出しなくても不動産投資は可能ですが、年間20万円を超える不動産所得がある場合は確定申告が必要となります。この際、開業届未提出では白色申告となり、青色申告の特典を受けられません。
白色申告と青色申告の違い
| 白色申告 | 青色申告 (10万円の特別控除) |
青色申告 (65万円の特別控除) |
|
|---|---|---|---|
| 申請書 | なし | 事前提出 | 事前提出 |
| 記帳方法 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
| 確定申告書類 |
|
|
青色申告決算書(正規の簿記の原則に従い記録している者) + e-Taxによる確定申告または優良な電子帳簿保存 |
| 特別控除 | 0円 | 10万円 | 65万円 |
青色申告では、記帳方法に応じて10万円または最大65万円の青色申告特別控除が受けられます(複式簿記に加え、e-Taxによる確定申告もしくは優良な電子帳簿保存をしない場合は最大55万円の特別控除)。
一方、白色申告には特別控除の特典がありません。青色申告でも簡易的な単式簿記で帳簿を作成した場合は、10万円控除が適用され、貸借対照表の提出も不要なため手続き面での負担は軽くなります。
青色申告特別控除を利用するには、収益が黒字で推移するタイミングまでに開業届を提出して個人事業主になっている必要があります。青色申告の各種メリットは赤字の年には活用できないため、黒字化を見込めるであろう2年目から積極的に活用することをおすすめします。
個人事業主として不動産投資を行う2つのメリット
個人事業主が不動産投資を行うメリットは、以下の2つです。
- 青色申告特別控除を受けられる
- 3年以内の赤字を繰り越せる
それぞれ詳しく解説します。
1. 青色申告特別控除を受けられる
個人事業主として開業届を提出することで青色申告が可能となり、青色申告特別控除を受けられます。控除額は記帳方法と申告方法により以下のとおりです。
- 10万円控除:単式簿記による記帳
- 55万円控除:複式簿記による記帳(貸借対照表の提出が必要)
- 65万円控除:55万円控除の要件に加え、電子申告または電子帳簿保存を行う場合
ただし、不動産所得で最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、事業的規模であることが条件です。事業的規模として認められるのは、「アパートは10室以上、貸家は5棟以上」で賃貸経営をしている場合です。
事業的規模と認められない場合には、青色申告特別控除額は10万円となります。副業で不動産投資を始めるサラリーマンの場合、多くは10万円の青色申告特別控除を受けることになるでしょう。
2. 3年以内の赤字を繰り越せる
青色申告では、不動産所得で生じた赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。この制度は青色申告特別控除の金額に関係なく、10万円控除でも適用されます。不動産所得が赤字となった場合には、給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算が可能です。ただし、土地取得のための借入金の利子部分は損益通算の対象外となるため注意が必要です。
また、損益通算後もなお赤字が残る場合、その金額を翌年以降3年間繰り越して、将来の利益と相殺できます。これにより、将来不動産投資が黒字化した際の所得税負担を軽減できます。この赤字繰越制度は、初期投資の大きい不動産投資において、サラリーマン投資家にとって重要な節税メリットといえるでしょう。
不動産投資で赤字、そんなときの損益通算には制限があります
個人事業主として不動産投資を行うデメリット・注意点
個人事業主として不動産投資を行うデメリットや注意点には、以下の2つが挙げられます。
- 開業届の提出などの手続きが発生する
- 一定規模を超えると個人事業税が発生する
それぞれ詳しく解説します。
1. 開業届の提出などの手続きが発生する
青色申告特別控除を受けるためには、税務署への開業届や青色申告承認申請書の提出が必要となります。65万円の青色申告特別控除を受けるためには、帳簿の記帳や領収書の保管など日常的な業務管理も必要です。
ただし、これらの手続きは決して「大きなデメリット」というほどではありません。現在では会計ソフトの普及により、比較的簡単に帳簿作成や申告書の作成ができますし、実際の負担はそれほど大きくないのが実情です。
2. 一定規模を超えると個人事業税が発生する
不動産投資では、原則として個人事業税の対象外とされています。不動産の貸付けは、一般的に事業というより資産運用の性格が強いと考えられているためです。ただし、以下の条件を満たす場合は、例外的に個人事業税の対象となる可能性があります。
- 事業的規模での運営
- 年間事業所得が290万円を超える場合
申告について所得税の確定申告を行っていれば、個人事業税の申告は不要です。都道府県が確定申告書の情報をもとに課税処理を行います。
サラリーマン投資家の多くは、事業的規模に達しないため、個人事業税が課税されるのは稀です。290万円を超える不動産所得を得られる段階では、すでに相応の収益を上げているため、大きな負担とは感じにくいでしょう。
不動産投資で融資を受ける際のポイント
サラリーマンが個人事業主として不動産投資で融資を受ける際には、審査で見られるポイントと融資を受けられる金融機関について理解しておきましょう。
1. 融資を受ける際に見られるポイント
金融機関は、以下の6つの項目を主にチェックします。
| 審査項目 | 詳細 |
|---|---|
| 資金 |
|
| 所得 |
|
| 勤続年数 |
|
| 支払いの延滞・滞納履歴 |
|
| 所属する会社の規模 |
|
| 現在の借入状況 |
|
これらの6つのポイントを意識して事前準備を行うことで、融資審査の通過率向上と有利な条件での借入れが期待できます。特に自己資金の蓄積と信用情報の管理は日頃から心がけておきましょう。
2. 融資を受けられる金融機関
個人事業主として不動産投資融資を受けられる主な金融機関は、以下のとおりです。
| 金融機関の種別 | 特徴 |
|---|---|
| 信用金庫 |
|
| 地方銀行 |
|
| ネット銀行 |
|
これらの金融機関にはそれぞれ異なる特徴があるため、自分の所属する企業や年収、投資物件に合わせて最適な融資先を選択しましょう。複数の機関に相談して条件を比較することで、より有利な融資を受けられる可能性が高まります。
不動産投資で個人事業主が法人化するメリット
個人事業主として不動産投資をする人が法人化するメリットは、以下のとおりです。
- 節税効果が個人事業主よりも高まる可能性がある
- 減価償却費の任意償却が可能になる
それぞれ詳しく解説します。
1. 節税効果が個人事業主よりも高まる可能性がある
法人化することで、より節税効果が高まる可能性があります。主な理由は以下のとおりです。
- 所得が大きくなると法人税率の方が有利になる
- 役員報酬として給与所得控除を受けられる
- 赤字を最長10年間繰り越せる
- 経費に計上できる費用の種類が増える
- 相続税対策として有効
個人の所得税は累進課税制度で、所得が増えるほど税率が高くなり最高45%に達します。一方、法人税は中小法人の場合、所得800万円以下の部分については15%、800万円超の部分は23.2%の一定税率です。年間所得が900万円を超える規模になると、法人税率の方が個人の所得税率よりも有利になります。
給与所得控除では、年収に応じて55万円から195万円の控除を受けられます。また、生命保険料や役員退職金などの優遇税制も活用可能です。さらに、役員社宅や出張旅費など、個人では経費にできない項目も法人では経費計上できるようになります。
個人が亡くなった場合は相続税が課税されますが、法人が所有する不動産であれば代表者が変更されるだけで所有者は変わりません。相続税を支払う必要がないため、節税へとつながります。
2. 減価償却費の任意償却が可能になる
不動産取得時の建物代金は、減価償却により複数年にわたって経費計上されます。建物の構造によって法定耐用年数が設定されており、この耐用年数に基づく償却率によって年間の減価償却費の上限が算出されます。
法人化することで、この減価償却費を経営状況に応じて柔軟に調整可能です。個人事業主の場合、毎年定められた減価償却費を必ず計上する必要がありますが、法人では任意償却が許されているため、経営状況に合わせた税務戦略を取れます。なお、年間の減価償却費の上限は決められているため、過去の減価償却不足分を損金算入額に加算することはできません。
たとえば、赤字傾向の年度は減価償却費を抑え、黒字幅が大きい年度には減価償却費を最大限に計上することで効果的な節税対策を実施できます。
不動産投資で個人事業主が法人化する適切なタイミング
法人化のタイミングは、サラリーマン大家か専業大家かによって異なるので注意が必要です。以下で詳しく解説します。
【サラリーマン大家の場合】
サラリーマン大家の場合、不動産事業が黒字で課税所得が900万円を超えると法人化の適切なタイミングといえます。課税所得900万円超の場合、個人では所得税33%と住民税10%を合わせて43%、法人では実効税率(法人税・地方法人税・法人住民税・事業税等の総合的税率)約23(800万円以下の部分)〜約35(800万円超の部分)%の税率となり、法人化による節税効果が明確に現れるのです。
【専業大家の場合】
専業大家の場合、事業所得が330万円を超えたときが適切なタイミングです。この段階での所得税20%と住民税10%を合わせて個人では30%〜、法人で実効税率約23%~約35%となり、個人税率の方が高くなります。ただし、不動産所得が330万円以下の場合は個人にかかる税率が所得税10%と住民税10%を合わせて20%と低いため、法人化はおすすめしません。
法人化のタイミングについては、個々の状況によって最適解が異なるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参照:No.5759 法人税の税率|国税庁
参照:No.2260 所得税の税率|国税庁
不動産投資で個人事業主が法人化する際の注意点
不動産投資で個人事業主が法人化する際には、以下の点に注意が必要です。
- 法人設立や維持に費用がかかる
- 赤字でも納税義務が発生する
- 複雑な手続きを行う必要がある
それぞれ詳しく解説します。
1. 法人設立や維持に費用がかかる
法人登記には登録免許税や定款認証手数料などの費用がかかり、設立時の司法書士費用や毎年の法人税申告のための税理士費用も発生します。また、帳簿の作成や社会保険の加入など、継続的な維持コストも考慮する必要があります。
会社設立時の具体的な初期費用は、実費だけでも株式会社の場合で約20万〜25万円、合同会社の場合で約10万円です。司法書士費用は依頼する事務所によって異なりますが、日本司法書士会連合会のアンケート調査では、会社設立登記における平均報酬は10万7,887円(※)でした。そのため、株式会社は30万〜35万円、合同会社では20万円程度を見込んでおきましょう。
確定申告の手続きや帳簿作成などが自分では難しい場合は、税理士に依頼する必要があるため、ランニングコストもかかります。
2. 赤字でも納税義務が発生する
法人の場合、赤字であっても均等割の法人住民税が課税されます。個人事業主時代は赤字の場合税金が発生しませんが、法人では最低でも年間7万円程度の法人住民税を納めなければなりません。法人化したタイミングによっては、個人事業主時代と比べて節税メリットが得られない場合もあるため、慎重な判断が求められます。
3. 複雑な手続きを行う必要がある
法人設立時には、定款作成や登記申請など多くの書類を作成する必要があります。また、会計帳簿の記帳方法が複雑化し、複式簿記の知識が求められます。さらに決算書類の作成や株主総会の開催など、定期的な法的手続きも発生するため、個人事業主時代と比べて事務負担が増大する点に注意が必要です。
個人事業主と法人化の違いを比較表で確認
ここまで述べてきたことを表にまとめると、以下のようになります。
| 比較項目 | 個人事業主(開業届あり) | 法人化(会社設立) |
|---|---|---|
| 税率 | 所得税の累進課税(5〜45%)+住民税10% | 法人税・法人住民税・事業税の法定実効税率
|
| 節税のしやすさ | 青色申告特別控除(10万円/65万円)が使える。(令和8年度税制改正で変更予定) | 経費計上の幅が広く、役員報酬など節税手段が増える。規模が大きくなるほど有利 |
| 赤字の繰越 | 3年 | 10年 |
| 設立コスト | 0円(開業届提出のみ) | 株式会社30万〜35万円、合同会社20万円前後(司法書士費用含む) |
| 維持コスト | ほぼ無し(会計ソフト等の小コストのみ) | 毎年最低7万円の均等割、税理士報酬10万〜30万円などが必須 |
| 赤字時の扱い | 赤字なら税負担なし | 赤字でも法人住民税(均等割)7万円〜が必ず発生 |
| 手続き・事務負担 | 単式簿記中心で比較的簡単 | 複式簿記必須。決算書作成・社会保険事務など負担が大きい |
| 社会保険 | 加入できない(国民健康や国民年金への加入が義務付けられている) | 社会保険加入が必須(健康保険・厚生年金への加入が義務付けられている) |
| 融資の受けやすさ | サラリーマン属性×個人名義で融資が通りやすい | 設立直後は実績がなく融資が不利。一定規模までは個人の方が強い |
| 経費の範囲 | 不動産収入を得るために直接必要な支出のみ経費化可能 | 役員報酬・会議費など間接的な経費も経費化可能。節税幅が増える |
| 向いている人 | 副業レベルの不動産投資/小規模の投資から始める人 | 所得が高い人、複数物件を保有し規模拡大を目指す人 |
| 注意点 | 所得が増えると税率が上がりやすい | コスト・事務負担が大きいので規模が小さいと逆効果になりやすい |
個人事業主・法人に関わらず不動産投資の成功に欠かせないこと
不動産投資の成功において重要なのは、信頼できる不動産投資会社をパートナーとして選ぶことです。
不動産投資は専門性が高く、物件選びから不動産の管理、経営、入居者との対応までさまざまな業務が発生します。目的に合わせた不動産選びに失敗すれば、空室リスクや出口戦略で悩み、損をする可能性も高くなります。
そのため、信頼のおけるパートナーを見つけて不動産投資の目的を明確にし、運営中の問題もサポートしてもらえる会社に依頼することが成功への近道となるでしょう。個人事業主として始めるか法人化するかという判断も、信頼できる専門家のアドバイスを受けながら進めることで、よりよい結果が期待できます。
個人事業主としての不動産投資にはさまざまなメリットがある
開業届を出して青色申告の個人事業主として不動産投資を行うことで、青色申告特別控除や最大3年間の損失繰越、幅広い経費計上など多くの税制メリットを享受できます。税務署への開業届や青色申告承認申請書の提出などがあり、若干の手間はかかりますが、得られるメリットを考えれば十分に価値のある選択といえるでしょう。
また、規模が拡大した段階での法人化についても、適切なタイミングを見極めることでさらなる節税効果を期待できます。どちらにせよ不動産投資を始める際に重要なのは、信頼できる不動産投資会社をパートナーとして選ぶことです。専門性の高い不動産投資であっても、信頼のおけるパートナーがいることで、長期的な視点で安定した投資を実現できるでしょう。
※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
関連キーワード