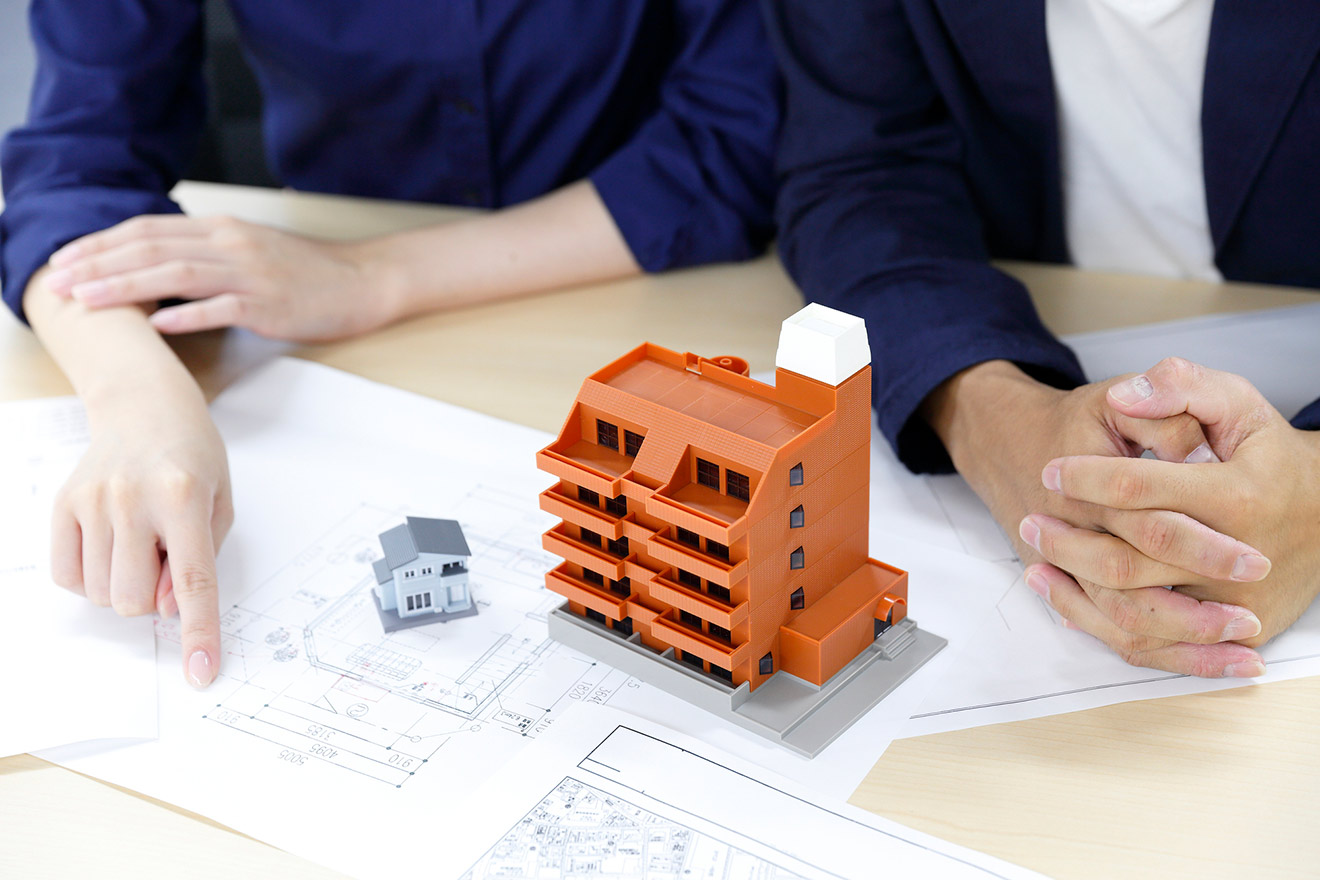不動産投資はいくらから始められる? 頭金や自己資金の目安を解説
「不動産投資を始める際の自己資金はいくら必要になるだろう?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
不動産投資における自己資金とは、ローンを利用して物件を購入する際に必要となる頭金や手付金、諸費用などです。物件価格の20%程度が自己資金の目安といわれることが多く、自己資金の考え方や目安を事前に把握しておくことで、物件購入時に慌てずにすみます。
本記事では、不動産投資を始める際の自己資金の内訳・目安や、金額別で購入できる物件の違いなどを詳しく解説します。
不動産投資はいくらから始められる?
不動産投資と聞くと「多額の資金が必要そう」というイメージを持つ方も少なくありません。しかし近年では、物件価格の大部分をローンでまかなえるため、自己資金が少なくても投資を始められるケースが増えています。
ただし、ローンを利用できる場合でも、手付金や各種手数料、税金などの初期費用は必要です。本章では、不動産投資を始める際の自己資金・頭金の目安や初期費用の内訳について解説します。
【初心者向け】不動産投資に最低限必要な元手はいくら?
1. 自己資金の目安は20%程度
不動産投資における自己資金の目安は、購入する物件の種類や売買形態、購入者の職業などによって変わりますが、一般的には物件価格の20%程度とされています。たとえば5,000万円の物件を購入する場合、自己資金として1,000万円を用意し、残りの4,000万円を金融機関からの融資でまかなうイメージです。
自己資金には、頭金・手付金・諸費用のすべてが含まれるため、頭金が求められるかどうかで必要な自己資金の額は大きく変わります。不動産投資会社や購入者の職業、信用力によっては、必要な自己資金が物件価格の1割以下ですむケースも珍しくありません。
たとえばRENOSY(リノシー)では、物件価格の全額融資を受けられる場合があり、自己資金10万円のみで投資を始められるタイプの不動産もあります。このように、自己資金の目安は一律ではなく、個々の状況に応じて柔軟に変わることを理解しておくことが大切です。
2. 頭金の目安は物件価格の10〜20%
頭金とは、物件の購入代金の一部として、ローンを利用せずに自己資金から現金で支払うお金のことです。一般的には物件価格の10〜20%が目安とされ、物件価格から頭金を差し引いた金額が金融機関からの融資でまかなう部分となります。
頭金はローンの借入時に支払うもので、投資用区分マンションなどでは、購入者の信用力や物件の資産価値によって頭金0円の「フルローン」で購入できるケースもあります。
頭金を多く入れると月々の返済額を抑えられるというメリットがある一方、手元資金が減少し、少ない自己資金で大きな収益を狙うレバレッジ効果が下がるという側面も考慮しなければなりません。自分の投資戦略や資金状況に応じて、頭金の額を決めることが重要です。
3. 手付金の目安は物件価格の5〜10%程度
手付金は、不動産を契約する際に契約の成立を証明するために、買主から売主に対して支払われる金銭のことです。一般的に物件価格の5〜10%程度が目安とされ、売買契約締結時に支払います。
契約が成立した場合、手付金は購入代金の一部に充当されるため、最終的な支払総額が増えるわけではありません。一方、契約が成立しなかった場合や契約違反があった場合には、手付金が解決の手段となります。
たとえば売主側の事情で契約が解除される場合には、購入希望者に手付金を返還し、同額を違約金として支払うのが宅地建物取引業法上の決まりです。なおRENOSY(リノシー)で不動産投資を始める際に必要な自己資金10万円は、この手付金に該当します。手付金はローンに組み込めないため、現金で用意しておく必要があることを覚えておきましょう。
4. 諸費用の目安は物件価格の8〜10%程度
不動産投資を始める際には、物件価格や頭金、手付金のほかに以下のような諸費用がかかります。
- 不動産会社に支払う仲介手数料(契約内容によって異なる場合があります)
- 印紙税
- 登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)
- 不動産投資ローンの保証料・事務手数料
- 火災保険などの保険料
- 不動産取得税
- 固定資産税・都市計画税(清算金)
- 管理費・修繕積立金(清算金)
諸費用の目安は、物件価格の8〜10%程度です。それぞれ詳しく解説します。
1. 不動産会社に支払う仲介手数料
不動産仲介手数料は、物件の売買を仲介した不動産会社に成功報酬として支払う費用のことです。宅地建物取引業法により上限額が定められており、物件価格が400万円を超える場合の計算式は「(物件価格×3%+6万円)+消費税」となります。
ただし、新築物件のように不動産会社が売主となっている物件を直接購入する場合、仲介行為が発生しないため仲介手数料はかかりません。購入を検討する際には、その取引が仲介か否かを事前に確認することが重要です。なお、RENOSY(リノシー)での取引では、お客様が売主であるRENOSYから直接物件を購入する形となるため、仲介手数料は発生しません。
2. 印紙税
印紙税は、不動産売買契約書や住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書など、特定の契約書を作成する際に課される税金です。契約書に記載された金額に応じて定められた額の収入印紙を貼り付け、消印することで納税します。
たとえば不動産売買契約書の場合、契約金額1,000万円超5,000万円以下で2万円、5,000万円超1億円以下で6万円です。現在は軽減措置が適用されており(令和9年3月31日まで)、1,000万円超5,000万円以下では1万円、5,000万円超1億円以下は3万円のように、本来の税額より低く抑えられています。
この印紙税は契約時に現金で支払うことが多いため、初期諸費用の一部としてあらかじめ準備しておく必要があります。
3. 登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)
不動産を購入すると、その物件が自分の所有物であることを法的に示すために「所有権保存登記(新築物件)」または「所有権移転登記(土地・中古物件)」を行います。所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、土地の場合、本則「固定資産税評価額×2%」(令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は1.5%)で、たとえば3,000万円の土地を購入する場合、「3,000万円×2%」で税額は60万円です。建物の税率は、自己の居住用ではないため軽減税率の適用はなく、新築の場合0.4%・中古の場合は2%です。
また、ローンを組む際には、金融機関が物件を担保に取るための「抵当権設定登記」が必要で、これらの登記手続きにも登録免許税がかかります。抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率は、「借入金額×0.4%」で、3,000万円を借入れする場合、税額は12万円となります。
このように、税額は固定資産税評価額やローン借入額に応じて決まります。登記手続きは専門知識を要するため、司法書士に依頼するのが一般的です。そのため、登録免許税の実費に加えて、司法書士への報酬(平均4〜10万円ほど)も登記費用として必要になります。
4. 不動産投資ローンの保証料・事務手数料
不動産投資ローンを利用する際、金融機関に対して事務手数料や保証料を支払う必要があります。事務手数料は、ローン契約手続きのための費用で、借入金額の1〜3%程度です。
一方、保証料は、万が一返済が滞った場合に保証会社に代位弁済してもらうための費用です。借入額の2〜3%程度を一括で前払いする方法と、ローンの金利に0.2〜0.3%程度上乗せして支払う方法があります。金融機関によっては保証料が不要なプランもあるため、ローンを選ぶ際の比較ポイントの一つとなります。
5. 火災保険などの保険料
不動産投資を行ううえで、火災保険への加入は金融機関から融資を受ける際の必須条件となることがほとんどです。火災だけでなく、落雷や風災、水災など、さまざまな損害から大切な資産を守る役割があります。
保険料は建物の構造や所在地、補償内容によって変動しますが、ワンルームマンションならば、火災保険の基本プランに施設賠償責任保険や地震保険を付けても年間2万円程度です。
なお、地震による損害は火災保険では補償されないため、必要な方は別途「地震保険」への加入を検討しなければなりません。地震保険は単独では加入できないので、火災保険とセットで申し込む必要があります。物件周辺のハザードマップなどを確認し、災害リスクに応じた適切な保険を選ぶことが、長期的に安定した運用につながります。
6. 不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を購入したり、贈与を受けたりした際に一度だけ課される地方税です。売買の場合は、土地と家屋それぞれの固定資産税評価額に対して原則4%の税率が適用されます。
この税金は物件購入時にすぐ支払うのではなく、取得から半年〜1年後くらいに都道府県から送られてくる納税通知書を使って納付します。そのため、購入時の初期費用とは別に、後から支払いが必要になる費用として忘れずに資金計画に組み込んでおくことが大切です。
7. 固定資産税・都市計画税(清算金)
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課される税金です。年の途中で物件の所有権が売主から買主に移る場合、引渡し日を基準日として、その年の残りの期間分を買主が負担するのが一般的です。
具体的には、引渡し日以降の税額を日割りで計算し、「清算金」として売買代金の決済時に売主に支払います。税額は市町村が決定する固定資産税評価額を基に算出されるため物件ごとに異なりますが、不動産を所有している限り毎年発生するランニングコストとして認識しておく必要があります。
8. 管理費・修繕積立金(清算金)
区分マンションを購入した場合、その年の管理費や修繕積立金のうち、売主がすでに支払っている費用があれば、引渡し日以降の分を日割り計算して買主が負担します。この精算も、売買代金の決済時に清算金として売主に支払うのが一般的です。
管理費は、廊下やエントランスといった共用部分の清掃や維持管理、管理人の人件費などに充てられます。修繕積立金は、十数年ごとに行われる外壁塗装や防水工事といった大規模修繕のために積み立てられるお金です。どちらも、マンションの資産価値を維持するために不可欠な費用となります。
【自己資金別】不動産投資に使える金額と購入可能な物件例
不動産投資を始めるために必要な自己資金が物件価格の20%という前提で、不動産投資にまわせる自己資金額で購入できる物件の価格と種類の目安を、以下の表にまとめました。
| 自己資金額 | 購入可能な 物件価格 |
購入可能な物件の種類 |
|---|---|---|
| 100万円 | 500万円 |
|
| 300万円 | 1,500万円 |
|
| 500万円 | 2,500万円 |
|
| 1,000万円 | 5,000万円 |
|
| 2,000万円 | 1億円 |
|
| 3,000万円 | 1億5,000万円 |
|
不動産価格が大きくなればなるほど運営にも費用がかかります。不動産投資にまわせる自己資金に余裕があるほど、物件運営の際の不測の事態にも対応しやすくなります。
不動産投資の自己資金はゼロにできる?
不動産投資でフルローンやオーバーローンを組めば自己資金がゼロになると考える方もいるかもしれませんが、完全にゼロにすることは難しいのが実情です。
その理由について、順を追って解説します。
1. 手付金はフルローンに組み込めない
手付金は不動産を購入する意思を示すためのものであり、現金で支払うのが一般的です。たとえフルローンを組んだとしても、少なくともこの手付金分の現金は用意する必要があります。
不動産投資を検討する際には、手付金を含めた初期費用をあらかじめ把握しておくことが重要です。
2. 自己資金を抑える方法もある
フルローンやオーバーローンを組むことで、頭金をゼロにし、自己資金を抑えられる場合があります。場合によっては諸費用もローンに組み込めるため、自己資金は手付金だけになります。
金融機関や不動産投資会社によって、フルローンやオーバーローンの対応の可否が異なりますが、この方法であれば頭金や諸費用を抑えることが可能です。しかし、自己資金を抑える分、月々の返済額が高くなる点には注意が必要です。
不動産投資の頭金をゼロにした場合のメリット
不動産投資の頭金をゼロにした場合のメリットは、以下のとおりです。
- レバレッジ効果を高められる
- 手元に資金を残せるので突発的な支出に対応できる
それぞれ詳しく解説します。
1. レバレッジ効果を高められる
頭金をゼロにすると、自己資金を使わずに物件を購入できるため、手元の資金を温存したまま複数の物件へ投資しやすくなります。結果として、少ない自己資金でより大きな資産を動かせる「レバレッジ効果」が高まり、家賃収入や物件の値上がり益を効率的に狙える点が大きなメリットです。
本来なら数年かけて貯める頭金を不要にできるため、投資開始のタイミングを早められることも魅力といえます。ただし、借入額が増える分だけ返済負担も大きくなるため、収支計画の精査は欠かせません。
2. 手元に資金を残せるので突発的な支出に対応できる
不動産購入時に自己資金をそれほど投入せず、手元に残しておくことで、購入後の運用に備えることが可能となります。不動産経営では、予期せぬ修繕やリフォーム費用、空室時の収入減少など、さまざまな事態に備えなければなりません。
さらに手元にある現金を、株式投資など別の投資にまわすことも可能となります。
自己資金ゼロで不動産投資を行う際のデメリット
手元資金を使わずに不動産投資を始めるのがベストかどうかは、考え方次第です。事前にリスクも把握しておきましょう。具体的なリスクは、以下のとおりです。
- 毎月の返済金額が高額になる
- 売却時にローン残債との差額調整が発生する場合がある
それぞれ詳しく解説します。
1. 毎月の返済金額が高額になる
自己資金なしでローンを組むと、借入金額が大きくなり、その分毎月の返済額も高くなりますし、家賃収入に占める返済の割合(返済比率)も上昇します。
そのため、家賃収入からローン返済や経費を差し引いた手残りの現金が少なくなることもあります。こうした状態で空室が発生したり、想定外の修繕費がかかったりすると、家賃収入が途絶えても返済は続くため、貯蓄を取り崩して補う必要が出てくる可能性も考慮しなければなりません。だからこそ事前に返済シミュレーションを入念に行い、毎月の返済額がどの程度になるかを把握しておくことが大切です。
2. 売却時にローン残債との差額調整が発生する場合がある
物件価格に加えて、初期費用分もローンに組み入れることも場合によっては可能です。これをオーバーローンといい、物件金額だけの借入れと比べて、より返済金額が高額になるのが特徴です。
オーバーローンで借入れを行うと、購入後に比較的短期間で売却をしようと思った際に、売却価格がローン残債を下回ることがあり得ます。売却するには金融機関の抵当権を抹消する必要がありますが、ローンが完済できないと抹消できません。そのため、不足分の資金を自分で用意しなければならなくなる可能性があります。
資産形成の戦略によって、自己資金を何にどう使うかは変わります。投資をスタートする前に、総合的に考えることが必要です。
不動産投資の出口戦略。成功するための4つの手法
不動産投資の頭金を入れた場合のメリット
不動産投資ローンを組む際に頭金を入れる場合のメリットは、以下のとおりです。
- ローン返済の負担を軽減できる
- ローンの審査を有利に進めやすくなる
それぞれ詳しく解説します。
1. ローン返済の負担を軽減できる
頭金の額が大きくなるほど、ローンの借入額が小さくなり、毎月の返済額を抑えられます。その結果、毎月の家賃収支においてその分手元にお金が残りやすくなるわけです。また、借入額が減るため、トータルの返済期間を短くできる可能性があり、利息の負担も軽減されます。
毎月の返済負担を軽減したい方や、早期にローンを完済したい方にとって、頭金を入れることは有効な選択肢となるでしょう。
2. ローンの審査を有利に進めやすくなる
頭金を入れることは、借主の資金力をあらわすため、信用力の評価につながる場合があります。資金力や計画性などがあると見なされれば、ローン審査を有利に進めやすくなります。
場合によっては金利が下がるといった条件の優遇もあるかもしれません。金融機関にとって、頭金を多く入れる借主はリスクが低いと判断されやすいため、融資条件が良くなる傾向があります。
不動産投資の頭金を入れた場合のデメリット
不動産投資ローンを組む際に頭金を入れる場合のデメリットは、以下のとおりです。
- レバレッジ効果が薄れる
- 手元資金が減少する
それぞれ詳しく解説します。
1. レバレッジ効果が薄れる
不動産投資は、借入れを活用して自己資金以上の規模で投資できる点に強みがあります。しかし、頭金を多く入れるほど借入割合が低くなり、レバレッジ効果は小さくなります。
本来であれば少ない資金で大きなリターンを狙える仕組みですが、頭金を入れることで投資に対する利益率が下がり、投資対効果も限定的になるわけです。安全性が高まる一方、資金効率の面ではデメリットとなる点を理解しておくことが重要です。
2.手元資金が減少する
頭金を入れて物件を購入すると、そのぶんだけ手元に残る資金は少なくなります。手元の現金が減ることで、急な修繕費や空室期間が発生した際に対応できなくなるリスクが高まります。
また「良い投資案件に出会ったのに、手元資金が足りず動けない」といった機会損失が起こりやすくなるのも懸念点の一つです。頭金を入れて安全性を高めたい場合でも、生活費や予備資金をどの程度確保するかを含めて、慎重に資金計画を立てておくことが欠かせません。
不動産投資ローンで審査される3つの項目
不動産投資ローンを組むとき、頭金を支払う必要性や金額を左右する可能性があるローン審査では、主に次の項目が審査されます。
- 個人の信用力(属性)
- 購入予定物件の収益性・資産価値
- 過去の不動産投資の実績
それぞれ詳しく解説します。
1. 個人の信用力(属性)
金融機関が不動産投資ローンの審査で重視するのが、物件の価値のほか、申込者個人の返済能力です。具体的には、以下のような項目が厳しくチェックされます。
- 年収
- 勤務先
- 勤続年数
- 雇用形態
- 年齢
- 信用情報(クレジットカードの支払い遅延など)
特に、収入の安定性が高いと評価される公務員や大手企業の正社員、勤務医、弁護士などは審査で有利になる傾向があります。安定した収入基盤があることは、万が一、家賃収入が途絶えた場合でも返済を継続できる信頼性の証となるからです。
2. 購入予定物件の収益性・資産価値
個人の信用力と並んで審査の柱となるのが、投資対象となる物件そのものの価値です。金融機関は、その物件が将来にわたって安定的に家賃収入を生み出せるか、万が一の際には売却して融資額を回収できるかを評価します。物件の評価ポイントは、以下のとおりです。
- 立地条件:駅からの距離、周辺環境
- 築年数・構造:耐用年数内で管理状態が良好
- 賃貸需要:空室リスクが低い立地
- 将来性:人口動態や再開発計画
- 担保価値:売却時の資産価値
収益性と資産価値が高い物件であれば、個人の信用力が多少弱くても融資を受けやすくなる可能性があります。
3. 過去の不動産投資の実績
初めて不動産投資を行う場合は関係ありませんが、すでに物件を所有している場合は、その運用実績も重要な審査項目となります。金融機関は、以下のような情報を確認し、申込者の不動産経営者としての手腕を評価します。
- 既存物件の家賃収入が安定しているか
- 空室期間が長引いていないか
- ローンの返済遅延がないか
良好な運用実績があれば、それが信頼につながり、次の物件購入の際の融資審査でプラスに働くでしょう。そのため、まずは小規模な物件からでも着実に実績を積み、段階的に投資規模を拡大していく戦略は、金融機関との良好な関係構築においても有効です。
自己資金を抑えて不動産投資を始める際のポイント
不動産投資ローンをうまく活用して自己資金を抑えたうえで不動産投資を始めるときは、以下のポイントに留意したいところです。
- 資産価値の高い物件を購入する
- 自身の信用力を利用する
- 不動産投資をサポートしてくれる会社を見つける
それぞれ詳しく解説します。
1. 資産価値の高い物件を購入する
不動産投資で重要なのは、物件そのものの資産価値です。市場価値の高い物件は、大きく以下の2つの特徴があります。
- 収益価値がある(安定した賃料収入が見込める)
- 売却価値がある(将来的に大きな売却益が見込める)
たとえば、立地条件の良い物件はこれらの2つの価値が高い傾向にあり、融資条件も有利になりやすいです。また、優良物件の特徴として、以下のような特徴が挙げられます。
- 交通利便性が高い
- 生活インフラが充実している
- エリアの人口動態が安定または増加傾向にある
- 建物の品質や管理状態が良好
- 安全性が高い など
このような資産価値が高い不動産ならば、たとえ自己資金が少なくても金融機関からの評価が高まり、融資を受けやすくなります。
2. 自身の信用力を利用する
不動産投資ローンにおいて、借り手の信用力、つまり個人の信用力(属性)の高さは重要な要素です。信用力を測る指標として金融機関が着目するのが、以下のような内容です。
- 勤務先の信頼度
- 勤続年数
- 職業の安定性
- 年収
- 金融資産の有無 など
これらの属性の具体的な評価基準は金融機関ごとに異なりますが、傾向としては、個人の信用力が高ければ少ない自己資金でも融資がとおりやすくなります。特に公務員や大手企業勤務者、医師(勤務医)などは、収入の安定性が高く評価され、融資条件が優遇されることもあります。
3. 不動産投資をサポートしてくれる会社を見つける
不動産投資を始める際には、単に物件を紹介するだけではなく、融資相談から物件管理、将来の売却まで一貫してサポートしてくれる会社を選ぶことが重要です。物件の購入だけでなく、その後の運用や出口戦略まで見据えたアドバイスを提供する会社は、初心者投資家にとって大きな味方となるでしょう。
特に少ない自己資金からスタートする場合は、専門知識や経験不足を補ってくれる信頼できるパートナーの存在が成功の鍵となります。総合的なサポート体制が整った不動産投資会社は、投資家の状況に合わせた柔軟な提案が可能で、限られた資金でも最適な投資プランを提示してくれる可能性があります。
不動産投資をいくらから始めるかは、物件や購入者の信用力によって異なる
不動産投資を始める際の自己資金の内訳と目安は以下のとおりです。
- 頭金:物件価格の10~20%
- 手付金:物件価格の5〜10%程度
- 諸費用:物件価格の8〜10%程度
これらをトータルで考えると、自己資金の目安は物件価格の20〜30%程度になるといえます。
ただし、これらはあくまでも目安で、必ずしもそれらを用意しなければ不動産投資を始められないわけではありません。
資産価値の高い物件を選んだり、個人の信用力を活用したりすることによって、不動産投資を始められます。また、不動産投資のサポートが充実した会社を選ぶことが成功の鍵となります。
※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。